
マンション総会は最低年1回! 基礎知識や出席率を上げる方法を解説

マンションの建物や敷地、附属する施設を管理するために、区分所有者(マンションの購入者)全員で構成される「管理組合」。マンションの維持管理を円滑に行うためにも欠かせない存在です。そこで、連載6回目では管理組合がそもそもどのような組織なのか、これから詳しくご紹介したいと思います。
マンションの管理組合は、維持・管理を行うために構成される組織です。管理対象には、建物そのものだけではなく、マンション敷地内にある付属施設も含まれます。
まずは、どのような人が管理組合員として活動しているのか、理解を深めていきましょう。
分譲マンションを購入したすべての人は、住戸(専有部分)の所有権を持つ「区分所有者」と呼ばれますが、本人の希望に関わらず「法律」上は管理組合の組合員になる必要があります。購入したものの別の場所に住んでいるという場合も、管理組合の組合員です。
ちなみに法律とは、区分所有者の持つ権利などを定めた「区分所有法」のことを指します。なお、分譲マンションを賃貸契約している人は組合員になる権利や義務はありませんが、住居に影響がある場合に限り意見を述べることができます。
管理組合の業務を円滑に進めるために、組合員の代表として「役員」が選ばれます。
役員は「理事会」を定期的に開催し、マンションの運営に関する事柄についての話し合いを主導で進めていきます。そしてそこで話し合われた内容を、定期的に開催される組合員全員参加の総会で、議題としてあげます。
なお総会の基礎知識や出席率を上げる方法については、以下の記事でも解説しています。
管理組合が組織されていると、「快適な住環境の維持」「トラブルの抑制」「資産価値の維持」といったメリットがあります。
集合住宅にはさまざまな人がいるため、管理組合が基本となるルールを定め、適切に守られるよう運用することで、住みやすいマンションを維持できます。
規則が定められており、仲介役として管理組合があれば、住民同士のトラブルもスムーズに解消または防止できるでしょう。
また、大規模修繕の実施や建物のメンテナンスも管理組合の役割の1つです。計画的に修繕費を集め必要な工事を行えば、マンションの資産価値も守れます。
区分所有者が組合員になるのは分かったけど「実際に何をするの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
組合員として関わる業務は、次の2通りあります。
・「理事会」の役員になる
・「総会」に参加する
それぞれの関わり方について具体的に見ていきましょう。
先に述べた通り、管理組合から選任された役員で理事会は組織されます。役員になること自体の義務はありませんが、立候補や推薦ではなく輪番制を採用しているケースも多いのが現状。つまり、多くのマンションでは、役員となる機会が区分所有者全員に等しく回ってきます。
理事会では役職が設けられるわけですが、主な役職に紐づく業務は次の通りです。
【理事長】
区分所有法において「管理者」と位置づけられ、管理組合の代表として管理規約や総会決議に従いながら業務を統括していきます。例えば理事会・総会における参加者の招集や、議長として各々の意見の取りまとめ、さらに印鑑(管理組合印)などを保管します。
なお理事長の権限や報酬、解任については、以下の記事で詳しく解説しています。
【副理事長】
理事長の補佐役として、場合によっては理事長が担う業務の代行を行います。
【会計担当理事】
管理組合の会計に関する業務を担います。管理組合の口座に入金された管理費等を管理し、必要な経費の支払いや、通帳の保管などを行います。また一年間の収入・支出をまとめた会計報告書を作成し、総会に提出する役目も負います。
【監事】
管理組合の業務進捗状況や財産状況などを監査して、総会で報告します。理事会での議決権はありません。
役員にならないとしても、区分所有者は総会に出席する必要があります。総会は年に一度開催される「通常(定期)総会」と、必要に応じて不定期に開かれる「臨時総会」があります。
ちなみに臨時総会では、修繕工事や管理会社の変更など、緊急で重大な議案がある場合に開かれることが多いようです。

前述の通り、区分所有者は主に「総会への参加」「理事の役員就任」を通してマンション運営にかかわります。ただし、本質的には区分所有全員が管理組合の組合員として運営・管理に携わっているのです。では、理事会を代表とする管理組合の成すべき業務とはなんでしょうか。
マンションは「専有部分」と「共用部分」に分けられますが、「専有部分」は区分所有者の持ち物にあたるスペースなので、管理は個々の責任となります。かたや、「共用部分」のエントランスホール・廊下・エレベーター・駐車場など、マンションの入居者全員が使用する場所は管理組合が主導して管理します。居住者が快適に過ごせるように清掃や建物の修理、設備の点検などの管理を行い、マンション全体に関する情報については、そこで暮らす人に共有をする必要があるのです。
また、マンションを購入すると、住宅ローンの返済以外に毎月「管理費」や「修繕積立金」がかかるほか、人によっては駐車場代も負担する必要があるでしょう。管理組合では、こうした管理費や修繕積立金といったマンションの所有者から毎月納めてもらうお金の、会計管理なども担います。
理事会とは上記で説明したような管理組合の実質的な運営を担当する機関を指します。清掃などの実務については委託した管理会社が担当するケースがほとんどですが、修繕によって発生する予算の承認のほか、管理規約の変更を議題としてあげるかどうかなど、重要な意思決定を担う機関だと考えていいでしょう。
理事会の構成メンバーは管理組合員のなかから総会で任命され、理事長や副理事長、そして理事数名と監事といった役職に分かれます。任期はおよそ1~2年で、再任も認められることがあります。一般的には1ヵ月に1回から2ヵ月に1回くらいのペースで会議を実施し、マンションの維持や管理、入居者の要望やトラブルなど、さまざまな事柄について話し合いを行っていきます。
ここまで聞くと「こんなにやることあるんだ……」と思うかもしれませんが、一般的にはマンション管理を専門に行う管理会社などに委託することが多いのではないでしょうか。もちろん管理組合が専門業者に直接依頼するなど、必ずしも管理会社に業務を委託する必要はありません。
なお、前述した修繕積立金や管理費については以下の記事で詳しく解説しています。
役員は通常、立候補か輪番制で決められますが、任命されたとしても辞退は可能です。法的な罰則などはありません。
しかし「大変そうだから」といった感覚的な理由で辞退する場合、他の理事会役員から不満が出ることも考えられます。輪番制で、誰にでも等しく役員の順番が回ってくるのであれば、なおさらです。
一部の人から不評を買ってしまうだけでなく、別の機会に面倒な役回りを任されたり、自分の意見が通りにくくなってしまったりといったデメリットも考えられます。
他者との関係性を良好に保ち、マンションの暮らしを少しでも快適にしたいと思うのであればなるべくなら辞退は避けたいところ。もちろん、海外赴任など正当な理由があれば別です。
ちなみに、マンションのなかには辞退者に一定の負担金や協力金を課すケースもあるようです。
いくら自分の住んでいるマンションだからといっても、すべての理事会役員が、必ずしも無報酬で業務に携わらなければならないわけではありません。
管理組合の合意に基づき、報酬を支払うこともできます。報酬の支払いは「役員のなり手がいない」「辞退者が続出している」という課題を抱える場合の解決策や、また業務の偏りからくる不公平感を是正するための措置となりえます。
ちなみに、国土交通省が2018年に行った調査によると、役員全員に報酬を支払っている管理組合の割合は全体の2割程度。理事に支払う報酬が役職関係なく一律の場合は、2000円以下が47.6%と、半数近くを占めます。
一方で理事全員の金額が一律でない場合、理事長の報酬額は1万円以上が20%と、最も多い割合です。監事を除くそのほかの理事の報酬額については2000円以下が46.5%と、やはり理事長など業務の負担が大きいと考えられる役職ほど、高い傾向にあります。とくに管理会社を入れていないマンションでは、支払う金額も高額になる可能性があるでしょう。
理事会の役員といっても、そのメンバーはマンションを区分所有する一般の人から構成されるわけですから、管理業務に関して専門的な知識を持っていない人がほとんどではないでしょうか。
しかし、これまで紹介した通りマンションの管理業務は多岐にわたり、専門的な知識が要求される内容も含まれています。さらに居住者の苦情に対応したり、保守・点検会社と交渉したり、時間や労力が相当かかる業務もあります。
そのため居住者の相談窓口や清掃業務、書類作成や会計管理などを中心に、マンション管理に精通した管理会社に委託して運営をサポートしてもらうケースがほとんどです。このように業務を委託する場合、管理会社に支払う費用はマンションの管理費のなかから捻出されます。
詳しくは下記の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。
マンションにおいては「管理員」がいるケースもあるでしょう。
ほとんどは契約している管理会社から派遣されるわけですが、具体的な業務としては、エントランスでの受付業務、来客や住人への苦情対応などを担います。
その他にも報告連絡業務の一環として掲示板にポスターやお知らせを掲示したり、共用部分の清掃をしたり、ゴミの収集に立ち会ったりするなど。マンションによって任せる項目は異なりますが、住民が気持ちよく暮らすための業務を担当してくれる存在といえるでしょう。
組合員全員でマンションの治安を守るのが管理組合ですが、法人となることも可能です。
法人化すると、管理組合名義の口座解説ができるため、管理費や修繕積立金の管理を代表者の個人口座で管理せずにすみます。
また、金融機関から修繕費などの借入ができたり、訴訟や調停の際に法人名義で行えたりといったメリットも。
総会での承認や登記の手間はありますが、理事会役員の個人の負担が減る可能性は大きいといえます。
詳しくは下記の記事でも紹介していうrので、参考にしてみてください。
マンションにおける良好な住環境を確保するために、さまざまな業務を請け負う管理組合。管理業務の一部は管理会社などに委託するケースがほとんどかと思いますが、管理にまつわる最終的な意思決定は管理組合、つまりマンションの所有者が行うことになります。
ここまで紹介してきたように改めて管理組合の役割を認識し、自分たちの暮らしを快適にするために工夫できることを考えていきましょう。
イラスト:大野文彰
マンションだからといって、購入後の管理はすべて管理会社にお任せ!というわけにはいきません。ほとんどのマンションにおいて、理事会の選考は立候補制ではなく、メンバーが入れ替わる輪番制。つまり、居住者誰もが理事会を担当する可能性が。というわけで本連載では、理事会役員になったらまず、これだけは知っておきたい!という超入門知識をご紹介。しっかり知識を身につけて、より良いマンションライフを送りましょう!
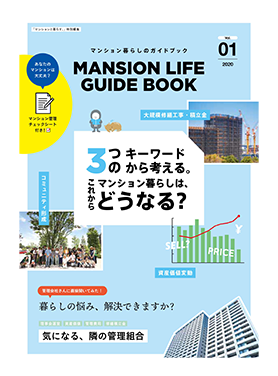
無料
ダウンロード
マンション居住者のお悩み解決バイブル!
最新マンショントレンドや理事会の知識など、
マンションで暮らす人の悩みや疑問を解決するガイドブック。
ここでしか手に入らない情報が盛りだくさん!
※画像はイメージです。実際のガイドブックとは異なる可能性があります。
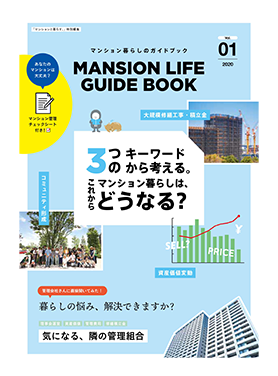 無料配布中!
無料配布中!