
マンションのベランダは共用部分に含まれる?トラブル事例も紹介

消防庁の発表によると、2023年に日本全国で発生した総出火件数は 3万8672件でした。これだけ多く起きている事実を考えると、「自分だけは大丈夫」と軽んじるべきではありません。
特に複数の人が共同で暮らすマンションの場合、自宅の火の元に厳しく注意していても、別の住戸からの出火によって火災に遭う可能性が考えられます。
リスクに備えるためにも、人や建物を火災から守る「防火管理者」について知っておきましょう。

防火管理者とは、建物における火災発生の防止や、火災が発生してしまったときに被害を最小限に抑える役割を持った防災の責任者です。
多くの場合、防火管理者は企業や飲食店などで必要とされるイメージがありますが、「消防法」の第8条第1項では「一定の要件を満たす建物では、管理権限を有する者は防火管理者を定めて、防火管理上必要な業務を行わせなければならない」といった旨の記述があります。
つまり、マンションを含む共同住宅も、この法律でいうところの「一定の要件を満たす建物」に含まれるため、防火管理者の選任が必要です。また、「管理権限を有する者」はマンションの場合は管理組合の理事長が該当します。そのため、理事長は管理組合員のなかから防火管理者を選任しなければなりません。
ただし、消防法には「収容人数が50人未満の共同住宅では防火管理者の選任が不要」とする規定もあります。マンションであっても、規模によっては選任が不要となる点も知っておきましょう。
防火管理者の役割である「防災管理上必要な業務」には、どのような内容が含まれるのでしょうか? 具体的な活動内容を見ていきましょう。
消防計画とは、火災などの災害の発生防止や発生時の被害の拡大を防ぐために立てられる計画です。
防火管理者は、管理する建物で火災を起こさないための予防策や災害発生時の対策方法、消防用設備の点検・整備、避難経路の維持・管理など、防災に関連する対応をマニュアル化して、計画書を作成します。作成した消防計画は管轄の消防署に届け出なければなりません。
消防計画の作成は難しく感じるかもしれませんが、消防庁や地方自治体のホームページから消防計画のひな形をダウンロード可能です。計画書の作成に苦労しそうなら、ひな形を確認して、どのような内容を記載するべきか参考にしながら作成してみましょう。

収容人数が50人を超えるマンションは、1年に1回の防災訓練の実施が義務づけられています。この防災訓練も防火管理者の担当業務です。
実施内容の例としては、火災発生時のマンション内周知や消防署へ通報を行う「通報訓練」、消火器や消火栓などを使って消火活動を体験する「消火訓練」、避難誘導などで安全な場所まで移動する「避難訓練」などがあります。適切に訓練しておけば、いざ災害が発生した際のスムーズな対応につながるので、真剣に取り組みましょう。
なお訓練を実施する際は、事前に「消防訓練実施届出書」を管轄の消防署に提出しておかなければなりません。

消火や避難の際に使用する、消火器、誘導灯、火災報知器などの点検もします。
マンションの場合、年に2回の消防設備の点検が義務づけられています。また、3年に1度は点検結果を管轄の消防署に報告しなければなりません。
災害時には屋外へ避難するために、ベランダを移動する場合があります。ただし、ベランダに大量の私物が置かれていると、避難の妨げになるかもしれません。
区分所有者の専有部分であると考えられがちなベランダですが、緊急時には避難に利用されるため、実際には共用部分です。
防火管理者は災害時に逃げ遅れる人が出ないためにも、定期的に避難経路を確認し、有事の際に問題なく利用できるように維持する必要があります。
防火管理者は、人と建物の安全に関わる重要な役割であるため、正しい知識を身につけていることが求められます。そのため、選任される人物は、防火管理者の資格を取得していなければなりません。資格は「乙種防火管理者」と「甲種防火管理者」の2種の国家資格に分かれており、管理できる建物の規模に違いがあります。
「乙種」は防火対象物全体の延べ面積が500㎡未満の建物であれば、防火管理者になれますが、それ以上大きな建物には対応していません。延べ面積が500㎡を超える建物の管理者となるためには、「甲種」の資格が必要です。
資格は講習の受講によって取得できます。乙種は、防火管理における基礎を中心としているため、5時間の講習を1日受講すれば取得できます。規模の大きな建物の管理も行える甲種の資格を取るためには、2日かけてトータルで約10時間の受講が必要です。いずれの資格の場合も、講習の最後に理解度測定のためのテストが実施され、合格すれば無事に資格取得となります。
講習の申込は消防署で受け付けています。各消防署や消防分署、消防出張所への申込用紙の持ち込み、またはインターネット、FAXで手続き可能です。
講習の受講には費用がかかりますが、金額は地域や受講する年によって変わります。概ね5000〜8000円が目安だと覚えておきましょう。

前述の通り、防火管理者の選任は法律で定められたルールです。建物の収容人数が50人以上あるマンションでありながら、防火管理者を選任していない場合は、罰則の対象となってしまうので注意しましょう。
消防法では、消防長または消防署長は、本来必要でありながらも防火管理者を定めていない建物の管理権限者に対して、管理者の選任を命じられると認めています。命令を受けたにもかかわらず選任しない場合には、管理権限者に6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
さらに、防火管理者の選任・解任時の届け出や防火対象物の点検の報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金又は拘留の対象です。
罰則を受けないためにも、管理権限者であるマンション管理組合の理事長は、防火管理者を選任するだけでなく、選任後に適切に機能しているかを監督するべきです。
火災は住む場所を失うだけでなく人命に関わる恐れがあるので、防災活動には真剣に取り組まなければなりません。日々、災害発生に備えておけば、被災した際に必ず役立つでしょう。
防火管理者の活動について、法律で厳しい罰則が設けられているのは、それだけ重要な役割だからです。罰則回避のためだけに仕方なく対応するのではなく、防災管理者が管理組合を巻き込み、マンション全体で防災意識を高められるように活動していきましょう。
イラスト:大野文彰
マンションだからといって、購入後の管理はすべて管理会社にお任せ!というわけにはいきません。ほとんどのマンションにおいて、理事会の選考は立候補制ではなく、メンバーが入れ替わる輪番制。つまり、居住者誰もが理事会を担当する可能性が。というわけで本連載では、理事会役員になったらまず、これだけは知っておきたい!という超入門知識をご紹介。しっかり知識を身につけて、より良いマンションライフを送りましょう!
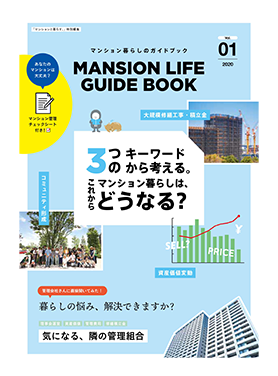
無料
ダウンロード
マンション居住者のお悩み解決バイブル!
最新マンショントレンドや理事会の知識など、
マンションで暮らす人の悩みや疑問を解決するガイドブック。
ここでしか手に入らない情報が盛りだくさん!
※画像はイメージです。実際のガイドブックとは異なる可能性があります。
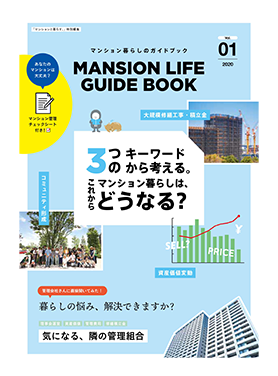 無料配布中!
無料配布中!