
理事会の運営で頼りになる「マンション管理士」の役割とは?

2001年8月1日に、日本で初めてマンション管理に関する法律として誕生した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、マンション管理適正化法)」。管理組合の理事なら知っておくべきマンション管理に対する姿勢や管理会社の義務などが規定されています。
2022年4月には改正法が施行され、適切な管理を行うマンションに地方公共団体が認定を与える「マンション管理計画認定制度」も開始されました。
そこでこの記事ではマンション管理適正化法内で定められているさまざまなルールについて、管理組合の理事が最低限理解しておくべき内容をピックアップして説明します。ぜひ、マンション管理の参考にしてみてください!
言うまでもなく、マンション内の管理や修繕は住民が快適に暮らすために非常に重要な業務。ですが、実は2001年8月1日にマンション管理適正化法ができる前は、建物内の所有権に関する規定(区分所有法)はあったものの、管理や修繕に関する明確な規定やルールは存在しませんでした。
マンション管理適正化法が施行された背景には、1990年代の集合住宅の急増とともに、居住者間の意識を合わせるためのルールがなければ、適切な管理や修繕を行うのが難しくなったという現状がありました。
例えば共用廊下の電球ひとつ交換するのにも、ルールがなく、気づいた人がやるのでは不公平感が生じます。交換する人がいなければ、共用部分の管理は放置されたままかもしれません。このような一部の入居者の善意の働きかけに頼る管理体制のままでは、将来的に居住環境が悪化するマンションが出てきても不思議ではありません。
そこで国が先導するかたちでマンションの管理に関するルールを法制化し、管理組合や住人、さらにはマンション管理業者に対して管理に関するそれぞれの義務を明確に定めることになったのです。
マンション管理適正化法では、マンション管理の主体は管理組合とマンションの住人であることを前提としています。とはいえ、適切な管理のために場合によっては外部の専門家や専門機関も必要となります。
そこでマンション管理適正化法において「マンション管理士」の資格制度を新設。従来より存在する管理会社については、管理業の登録と「管理業務主任者」という専門資格保有者の設置を義務付けました。
さらに、日常の管理業務などに関する相談窓口として公益財団法人「マンション管理センター」を設置。相談は電話や対面、メールなどにより可能で、マンション管理に関する法律などをもとに中立的な立場でのアドバイスが受けられます。
なお理事会のサポートを行うマンション管理士の役割について、以下の詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
マンション管理適正化法では、マンション管理の適正化を図るために「マンション管理適正化指針」を盛り込んでいます(第3条)。このなかで、住人一人ひとりが積極性を持ってマンション管理に関わり、その役割を適切に果たしていかなければならないと定めています。
ではこの指針、具体的にどういった内容なのでしょうか。6つある項目のなかでも、特に管理組合が参考にしたい内容のみに絞り込んで紹介していきます。
管理組合を主体とした管理を基本とし、必要に応じて第三者(マンション管理会社など)に管理業務を委託する場合は、内容を十分に検討して契約を締結しなければならない。
管理組合の運営は、情報を開示し、運営の透明化を図るなど民主的である必要があります。また管理組合は管理規約の作成と改定を適宜行い、長期修繕計画についても策定および適宜見直しを行うことが大切です。
これからマンションを購入しようとする人は、マンション管理の重要性を十分認識し、区分所有者として管理組合への参加と管理規約を守ることが必要です。
管理組合が管理会社を選ぶ際には、事前に資料を収集し、住人に対してその情報を公開しなければなりません。万が一、管理会社による業務に問題が生じれば、管理組合は業者に対して解決を求める必要があります。
管理組合はマンション管理の適正化をはかるため、必要に応じてマンション管理士など専門知識を有する者の知見を活用していきましょう。

マンション管理適正化法では、管理組合や住人のみならず、管理会社が果たすべき義務も規定しています。以降で代表的な義務の一部を紹介しますので、委託している管理会社がしっかりとこのルールに沿って業務を行っているか、照らし合わせてみましょう。
マンション管理業を営むには、国土交通省が管理する「管理業者登録簿」に登録されなければなりません。登録の有効期間は5年。5年を過ぎたときには、更新手続きが必要となります。
管理会社は、業務の委託を受けた管理組合に対して30組合につき1人以上、専任の管理業務主任者を置かなければなりません。ただし、居住者が5人以下の管理組合については管理組合数にカウントしないものとします。
ここで、管理業務主任者とは「管理業務主任者試験」に合格し、かつ2年以上の実務経験、あるいは登録実務講習の修了試験に合格した場合に得られる国家資格のこと。資格の有効期間は5年で、更新には申請による手続きが必要です。
なお、管理業務主任者はマンション住人の申し出に応じて、主任者証を提示する義務があります。
管理会社は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省で定める標識を掲げる必要があります。なお、国土交通省へ登録を済ませることで、管理業者であることの標識の提示が可能です。
管理会社と管理組合が委託契約を結ぶ際、管理業務主任者からマンション住人に向けた説明会を行わなければなりません。説明会の内容としては、管理業務の内容や財産の管理方法など。
説明会の開催日時と場所は、開催1週間前までにマンションの全ての住人に告知し、事前に説明会の内容を記載した書面を渡しておく必要があります。
管理組合と委託契約を結ぶとき、管理会社は契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。書面には、管理業務主任者の記名と押印が必要となります。
管理組合から委託を受けた管理業務については、再度、他の管理会社などに一括して委託することができません。
管理組合の修繕積立金などの財産は、管理会社の財産とは別で、分別して管理する必要があります。
管理会社は管理組合の会計業務などの基幹事務については、一括して他人に委託することはできません。
逆にいうと、基幹事務以外、例えば清掃や草木の剪定、設備の修繕・維持などの業務については、第三者に委託することも可能といえます。
管理会社は管理組合に対して、定期的に管理業務主任者から管理業務に関する報告をしなければなりません。「定期的」というのは、「管理組合の事業年度終了後、遅滞なく」とされています。
マンション住人から業務内容や財産状況の書類の開示を求められた場合、それに応じなければなりません。
管理会社などは、これまで説明してきた義務に違反すると、国土交通大臣から業務停止命令や登録の取消しなどの処分を受けることになります。
管理会社は、管理組合の1カ月の支出入状況を書面にて報告する必要があります。
2001年に制定された「マンション管理適正化法」は2020年に改正され、管理の適正化に向けた目標設定や建て替えの合意形成、知識の普及を促進するための事項が追加されています。
また、地方公共団体による管理適正化も推し進められています。地方公共団体が策定した「マンション管理適正化推進計画制度」に則って各管理組合が計画を作成する制度が設けられたほか、都道府県等から管理者に対して指導・助言、勧告が可能となりました。
次項で紹介する「管理計画認定制度」も、この度の改正で新設された制度です。
前述のとおり、マンション管理適正化法の改正に際して「管理計画認定制度」が設けられました。
認定制度とは、マンションの管理・運営が適切に行われているかどうかを評価し、一定の基準を満たした物件は市町村などの地方公共団体が認定を与える制度です。
基準となるのは、修繕を含む管理方法、資金計画、管理組合の運営状況など。管理組合の規約や役員が定められていない、また修繕計画が立てられていないマンションの実態を把握するとともに、管理への意識を高める目的があります。
今回のマンション管理適正化法の改正に先駆けて、2021年9月に長期修繕計画作成および修繕積立金のガイドラインが改訂されています。
これにより、従来25年とされていた長期修繕計画は30年に変更され、より長期的な視点が求められるようになりました。計画の見直しについても「随時」とされていましたが、「5年程度」と明確化されています。修繕積立金の計算式も、より実態に即した式に見直されました。
見直しには、マンションの築年数が全体的に上がっている点や、機械式駐車場やエレベーターといった設備費の高騰が考慮されています。
また、改訂前はタワーマンションの事例が少なかったと考えられます。現在は、20階以上のマンションの積立金額の目安が実態に即して引き上げられているため、タワーマンションの人にとっては影響が出てくる可能性があるでしょう。
新築マンションにも「予備認定」といって、認定制度が適用される予定です。
マンション管理センターから予備認定を受けたマンションを購入する場合、「フラット35」の金利が一定期間引き下げられるメリットがあります。
認定制度によってますますマンション管理の適正化が促進すると考えられるでしょう。
マンション管理適正化法からもわかる通り、マンションの管理は管理組合とマンションの住人のみならず、管理会社などの第三者の協力も不可欠。必要に応じてマンション管理士やマンション管理センターなどにも相談しながら、健全なマンション管理を実施していきましょう。
イラスト:大野文彰
マンションだからといって、購入後の管理はすべて管理会社にお任せ!というわけにはいきません。ほとんどのマンションにおいて、理事会の選考は立候補制ではなく、メンバーが入れ替わる輪番制。つまり、居住者誰もが理事会を担当する可能性が。というわけで本連載では、理事会役員になったらまず、これだけは知っておきたい!という超入門知識をご紹介。しっかり知識を身につけて、より良いマンションライフを送りましょう!
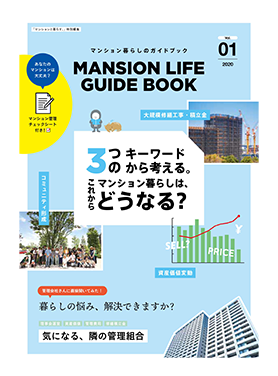
無料
ダウンロード
マンション居住者のお悩み解決バイブル!
最新マンショントレンドや理事会の知識など、
マンションで暮らす人の悩みや疑問を解決するガイドブック。
ここでしか手に入らない情報が盛りだくさん!
※画像はイメージです。実際のガイドブックとは異なる可能性があります。
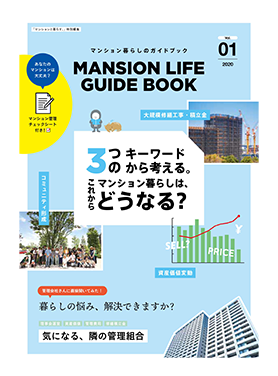 無料配布中!
無料配布中!