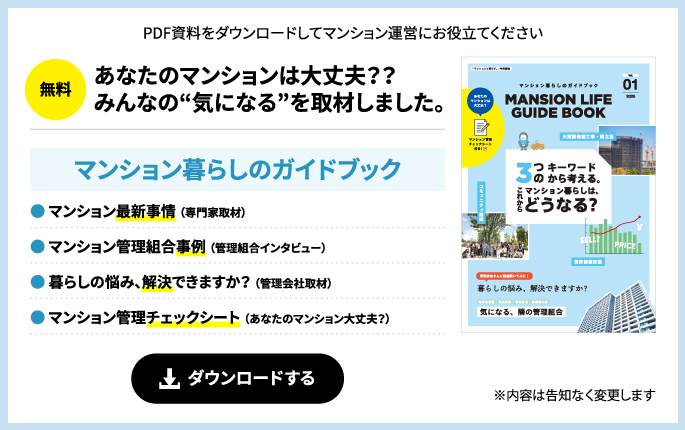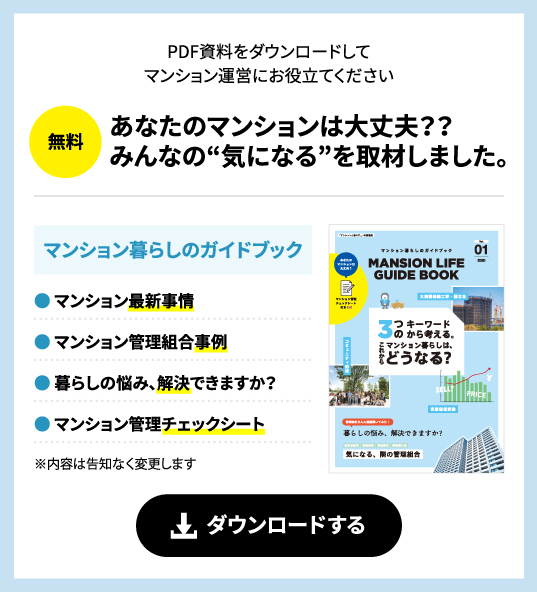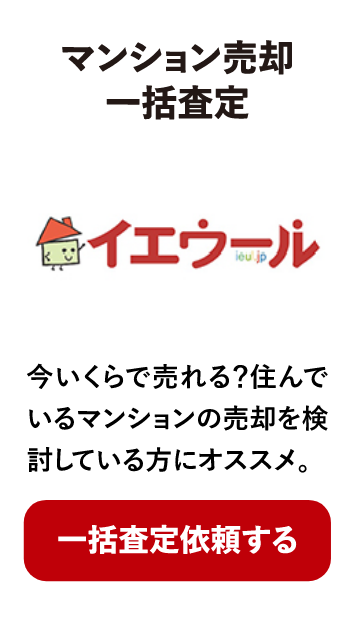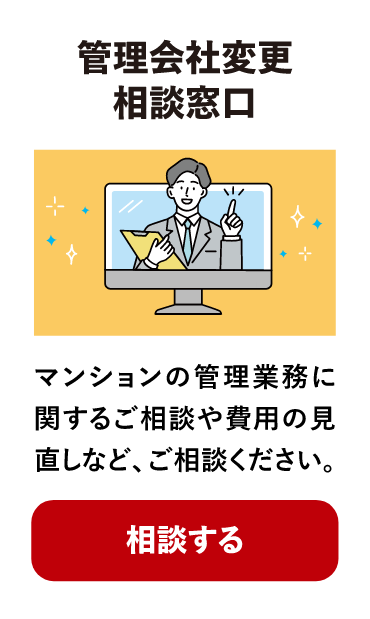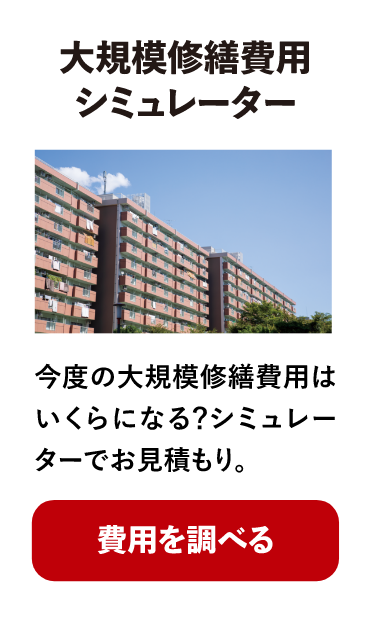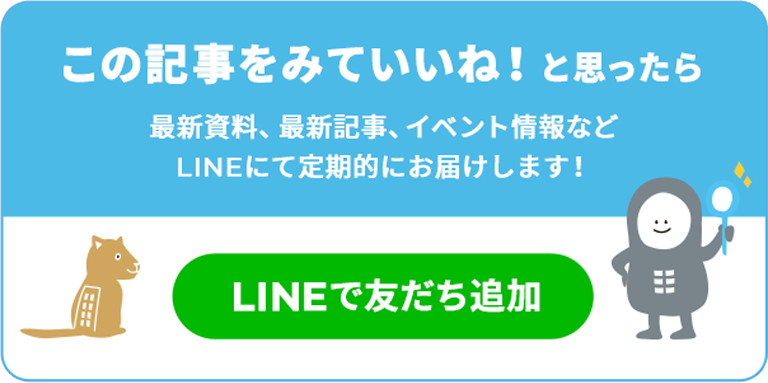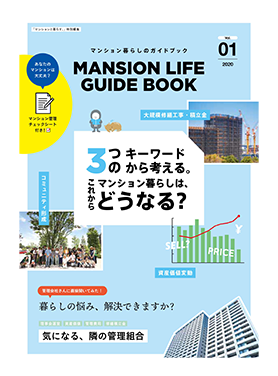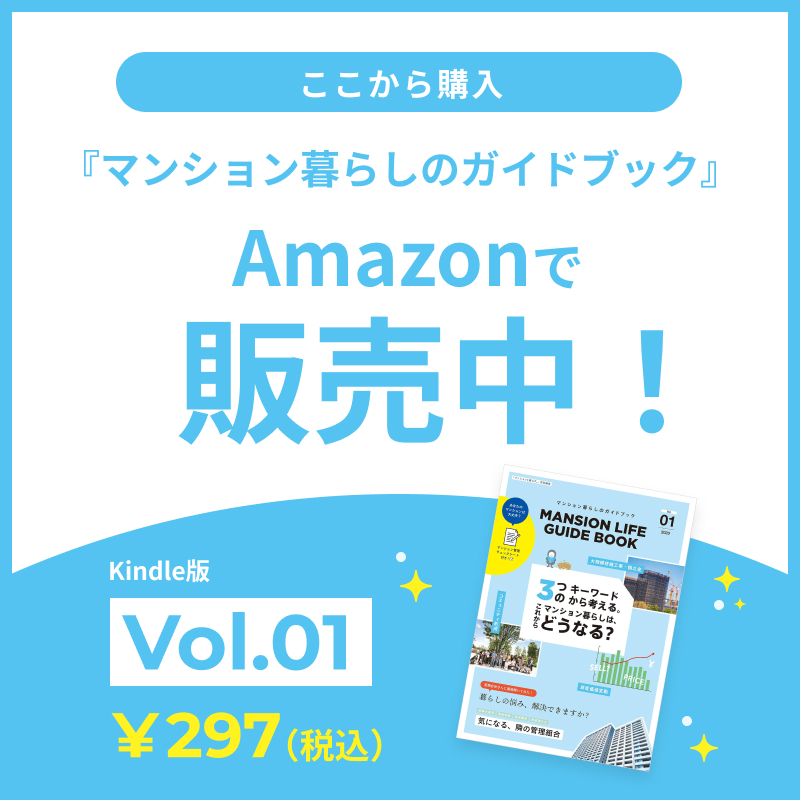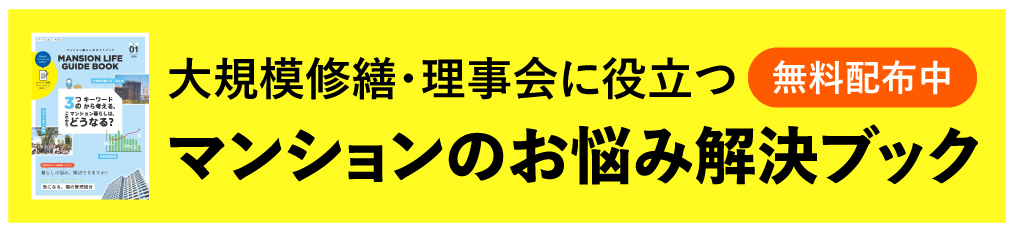連載
連載
建物診断の相場は20万〜100万円! 経年劣化や耐震性がわかる

マンションの劣化具合などを把握するためには、建物診断が不可欠。「経年劣化」「配管劣化」「耐震」「収益性(資産価値)」を診断することで、精度の高い長期修繕計画の作成が可能です。
事前に工事箇所が明確になっていれば、正確な修繕費用が把握できるため、資金計画も立てやすくなるでしょう。
ここではそんな建物診断について目的やメリットを改めて整理するとともに、相場なども紹介していきます。
建物診断で長期修繕計画の妥当性が分かる
建物診断とは、マンションがどの程度劣化しているかを確認するために行われる現地調査のこと。人間で例えるなら、健康診断のようなものです。
マンションの大規模修繕は、長期修繕計画をもとに12~15年周期で行われるのが一般的。ただこれはあくまでも計画にすぎないため、事前調査として建物診断を行い、現在の劣化・不具合状況を把握する必要があるのです。
建物診断を行うことで長期修繕計画とのズレを把握でき、大規模修繕の実施時期の検討や予算の計画に役立てることができます。
さらに大規模修繕を実施する施工会社を選ぶ際、各社に見積もりをお願いすることになるかもしれません。このとき正確な工事費用を知るためにも、建物診断にもとづいた設計書が必要となるのも理由の一つです。
診断項目は「経年劣化」「配管劣化」「耐震」「収益性」の4つ
業者によって異なりますが、診断項目としては「経年劣化」「配管劣化」「耐震」「収益性」の4つ。それぞれの内容と相場を見ていきましょう。
【項目1】経年劣化診断
建物がどれだけ傷んでいるか、目視や触診で確認するのが「経年劣化診断」です。屋上防水や外壁、鉄部などが調査の対象となります。
屋上防水やシーリング材などの劣化具合を手で触ったり、外壁や床を叩いたときの音で浮きや剥離などの異常を確認したりしながら、調査は実施されます。
主なチェック項目は次の通りです。
・タイルが浮いたり、剝離したりしていないか
・剥離している場合、接着剤の劣化状況はどうか
・コンクリートの劣化状況はどうか
・内部鉄骨の錆びや膨張の状況はどうか
・施工ミスによる瑕疵などはないか
一般社団法人建築診断協会によると、経年劣化診断の相場はマンション1棟あたり20万円〜となっています。
【項目2】配管劣化診断

目視では確認が難しい配管の劣化を確認するのが「配管劣化診断」です。「内視鏡調査」「超音波検査」「X線調査」「サンプリング調査」という4種類の調査方法があります。
各調査の特徴をざっくりと見ていきましょう。
・内視鏡調査
ファイバースコープやビデオスコープを使用して観察。肉眼では見ることができない配管内の汚れや劣化・腐食状況などを確認する際に役立つ
・超音波検査
配管の外側から内側に向かって超音波を当てて、対象物からの反響を映像化する
・X線調査
配管内面の腐食や付着した異物の状況を調べるため、工業用X線装置により透過撮影を行う
・サンプリング調査
配管ごと縦に二分割して内面を洗浄し、腐食状況を確認する
このように表面には表れてこない劣化具合に関しては、専用の機器を使って診断します。
NPO埼玉マンション管理支援センター価格表によると、配管周りの診断は約20万円程度とされています。
【項目3】耐震診断
地震国である日本では、マンションの性能を考えるときの大切な要素の一つが耐震基準です。
耐震基準は1981年、2000年、2007年にそれぞれ変更されており、年数を経るごとに基準が厳しくなっています。つまり、昔の基準で建築された建物ほど、耐震性能が低いのです。
どれくらい大きな地震に耐えられるのかは、あくまでも現在の基準に当てはめて確認する必要があります。
一般社団法人建築診断協会によると、相場は鉄骨造で20万円〜、鉄筋コンクリート造で40万円〜となっています。
【項目4】収益性(資産価値)診断
建物診断では調査の結果から収益性(資産価値)も導き出してくれます。
自分たちの住むマンションが、周辺地域の他の建物と比べて、どの程度の資産価値があるのか把握する際に役立つかもしれませんね。
もし、中古であっても新築時と変わらない資産価値を維持しているのであれば、購入したいと思う方も増えるでしょう。若い世代の購入者が増えれば、マンション内部の雰囲気も若返るかもしれません。
一般社団法人建築診断協会によると、相場は賃貸住宅の場合で10万円〜となっています。
合計の費用相場は規模によって20万〜100万円
目視調査や打診調査など、簡易的な調査方法であれば安く済みます。一方で、配管劣化診断など専門の機器を使った調査などは高額になる可能性があるでしょう。
なおあくまでも目安となりますが、マンションの規模ごとの調査費用はだいたい以下の通り。
・小規模マンション(30戸以下が目安)の場合は、20万~40万円
・中規模マンション(50~100戸が目安)の場合は、30万~80万円
・大規模マンション(200戸以上が目安)の場合は、50万~100万円
正確な調査費用が知りたい場合は、まず業者に見積もりを依頼することから始めてみましょう。
建物診断を実施する2つのメリット
建物診断を行うメリットについて、改めて2つにまとめました。
【メリット1】建物全体の劣化具合を把握できる
前述した通り、建物診断を行うことで建物全体の劣化具合を把握することができます。
そして診断結果にもとづいて修繕箇所の優先度もわかるため、今度の大規模修繕では「どこを工事して、どこは必要ない」という計画が立てられるわけです。
劣化具合に応じた修繕が可能となるため、無駄な工事を省き、結果的に費用の削減にもつながるかもしれません。また、現在の資産価値はどの程度なのかも把握できます。
【メリット2】パッと見ではわからない修繕箇所の把握にも役立つ
外から見ると劣化してないように見える箇所でも、内部は修繕の必要があるケースもあります。
その点、建物診断では専門的な視点から、資産価値に影響を及ぼしそうな劣化箇所を、見える化してもらえるでしょう。
建物診断が必要な理由はズバリ資金調達
劣化の程度がわかるため修繕の優先順位が付けられる、という建物診断のメリットは先に述べた通りです。
つまり、建物診断を行うと必要な工事だけ実施できるほか、劣化の程度に合わせた施工方法を選べるため、必要以上の費用をかけずに済むのです。
具体的な修繕計画も立てられるため、実際に必要な工事費用とのギャップも生まれにくく、修繕積立金が足りないといった事態を防げます。
また、修繕工事の相見積もりを取る際にも、工事項目が明確になっていると、価格を比較しやすいです。適正なコストを見極めるうえでも、建物診断は重要といえます。
診断のタイミングは築20年が目安
建物診断を行うタイミングは、主に次の4つです。
【タイミング1】築20年以降
マンションは築20年も経過すると、外壁といった外部の劣化だけでなく、配管など普段は目に見えない場所の修繕も必要になってきます。
そのため、目視や打診といった簡易的な調査だけでなく、給・排水管などの設備も含めて広範囲の診断を行いましょう。
【タイミング2】アフターサポートの期限が切れる10年以内
分譲マンションは、基本的に引渡しの日から最低10年間は売主は瑕疵担保責任を負わなければいけません。
そのため保証が効く、10年以内に「建設時の施工不備」はないか、建物診断を行いましょう。瑕疵が見つかり、売主に修繕費用を負担してもらえる可能性もあります。つまり、その分管理組合側の金銭的な負担は軽減するかもしれません。
【タイミング3】長期修繕計画の作成時
建物診断を行うことで、マンションの劣化状況に合った修繕時期や工事箇所を盛り込んだ長期修繕計画の作成が可能です。
正確な修繕費用も把握できるでしょうから、適正な修繕積立金の金額を算出する際にも役立ちます。
【タイミング4】大規模修繕を実施する前
最初に触れた通り、修繕工事を行ってもらう施工会社を選ぶ際、各社に正確な見積もりをお願いするために修繕箇所を記した設計書が必要となります。
この設計書を作成するために、「どこを直して欲しいのか」事前に建物診断を通じて把握しておく必要があるのです。
診断の期間は1〜2日程度!
建物の規模やどの程度細かく診断するかにもよりますが、診断にかかる期間は50〜100戸のマンションで1〜2日程度です。
なお、報告書が提出されるまでには約1ヵ月程度の期間を見ておくといいでしょう。
建物診断は管理会社で行ってくれる場合もある
建物診断の依頼先を見つける最も簡単な方法は、ネットで「建物診断 業者」と検索するやり方です。
建物診断を専門に行っている企業が複数見つかるため、対象地域に当てはまっているかどうかを確認したうえで、いくつかの企業のウェブサイトを見比べてみましょう。価格は見積もりを依頼して初めてわかる点もあるため、まずはサイトの見やすさやわかりやすさで判断するのもひとつの手です。
管理会社によっては、マンションの管理・運営のほかに、建物診断を請け負っているケースもあります。もしくは、建物診断を実施できる業者を紹介してくれる可能性もあるでしょう。
ネットでの検索と併せて管理会社へも尋ねておけると万全です。
問合せ方法と診断の流れ
業者によってもちろん異なりますが、建物診断の主な申し込み方法から診断の流れも以下で紹介していきます。
【手順1】メールや電話で問い合わせる
当然のことですが、建物診断の問い合わせは各業者の公式サイトに記載のあるメールや電話、また問い合わせフォームなどから行います。相談内容のヒアリングから診断実施の擦り合わせ、また建物診断完了後の報告までの流れなどを教えてもらえます。
【手順2】打ち合わせをする
メールや電話で聞ける場合もありますが、実際に打ち合わせの場を設けて、診断内容や費用について詳細を聞きます。
【手順3】見積もりをとる
現地訪問の前に、建物の大きさや立地、図面などの設計資料、過去の修繕や点検に完成する書類をもとに概算費用の見積もりを出してもらいます。
ただし、業者によっては対応していなかったり、資料が不足していると判断できなかったりするため注意が必要です。
【手順4】住民へのアンケートを実施
各戸で漏水や、バルコニーの劣化などの不具合がないか、事前の意見を聞きます。生活しているなかで気づくような問題点を把握できるため、現地調査だけではわからない工事箇所を確認するのに役立ちます。
【手順5】目視・打診による現地調査
事前に設計資料やアンケートを踏まえ、現地での調査が行われます。
外壁や屋上、階段といった共用部を中心に調査を行います。なお、バルコニーの調査が必要名場合は、部屋の中を通る必要があるため、事前に実施の有無を確認しておきましょう。
現地調査が終わると、診断計画書や見積書が作成されます。診断内容と費用に同意したら契約を交わし、実際のさらに具体的な調査に移ります。
目視で確認しながら、打診棒という器具で壁などを叩き、反響音で状態を判断します。
場合によっては、専用の機械や薬品を使って、コンクリートの品質やタイルの剥離状態をします。
【手順6】診断結果の報告
最後は現地調査をもとに建物の分析が行われ、作成した報告書をもとに診断結果を説明してくれます。
無料で診断できる場合もある!
建物診断には費用がかかるケースがほとんどですが、無料診断を実施している業者もあります。
有料で行われる診断より簡易的なものになるため、住民への事前アンケートや専門の機械を用いた診断はされない可能性が高いといえます。
それでも、目視や触診、打診による調査は行われるため、ある程度の劣化や不具合はわかるでしょう。
劣化状況を正確に把握するために建物診断は大事!
正確な長期修繕計画を作成する際に役立つ建物診断。修繕箇所の優先順位などもわかるため、不要な工事は後回しにできるなど、当初予定していたよりも修繕費用を抑えられる可能性もあります。
なお、今回紹介した建物診断の費用はあくまで目安。そのため、正確な費用は業者に見積もりを依頼してみましょう。
大規模修繕工事費用を自動見積もりする!
気になる大規模修繕の工事費用。「マンションと暮らす。」を運用するカシワバラ・コーポレーションでは、マンションの概要を入力いただければ、大規模修繕費用を自動でお見積もり。大規模修繕を控えたマンション理事会、大規模修繕委員会の方におすすめのサービスです。