
人が不快に感じる音の度合いとは?「騒音レベル」について知ろう!

騒音はマンションで暮らす多くの住人が抱える問題の1つです。隣人からの騒音に悩まされることはもちろん、気づいたら自分が加害者になっていたということもあり得ます。そんなとき、トラブルを大きくしないためにも具体的な対処方法について知っておくことが大切です。
そこでここでは、騒音トラブルに巻き込まれたときの対処法について解説。騒音問題で、裁判にまで発展したケースもあわせて紹介していきます。
「そもそもどんな音が騒音になるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。結論から言うと、生活するうえで発生するほぼすべての音が騒音の原因となる可能性があります。
騒音の具体例をあげると次の通り。
・上層階からの足音
・話し声
・ピアノなどの楽器や音楽機器
・洗濯機や掃除機といった生活家電の稼働
子どもが走り回る音だけでなく、夜勤の仕事で早朝に食事の準備を行うなど、生活習慣の違いで発生する足音もあります。大きな声での電話や、2〜3人ぐらいの井戸端会議が騒音になってしまうケースもあるでしょう。
また、マンション内のルールとして楽器を演奏して良い時間帯が定められている場合でも、過剰に大きな音は騒音につながってしまう恐れがあります。
前提として、音量や周囲の感じ方によるものの、身近な音すべてが騒音になり得るということは理解しておきたいところ。自分が被害者になることはもちろん、知らないうちに周囲に迷惑をかけている可能性もあり得るのです。
騒音レベルについては以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
では、実際に騒音トラブルに巻き込まれたらどのように対処すればいいのでしょうか?
ここからは騒音被害に悩まされている場合の対処方法について解説していきます。
騒音被害の対処方法として最初に考えたいのは、マンションの管理会社への相談です。
騒音問題は当人同士で解決できるのが一番です。しかし、直接苦情を言うことで相手の反感を買ってしまい逆に嫌がらせが始まるなど、騒音以外のトラブルに発展する可能性もあります。そこで注意をするにしても、直接ではなく管理会社などの第三者にお願いしたほうがベターです。
管理会社が行ってくれる対応としては、張り紙や手紙による注意喚起など。もし管理会社から注意されたにもかかわらず騒音をやめない、あるいはさらにひどくなったという場合は、以下の相談先も検討してみましょう。
・自治体の生活相談センター
場合によっては仲裁や専門家の紹介をしてもらえる
・警察
事情を説明のうえ、被害届けを提出できる
・弁護士
訴訟や調停の手続きができる
警察が注意しても収まらない場合、弁護士への相談も視野に入ってくるでしょう。裁判所が判決を下す「訴訟」ではなく、あくまでも話し合いによる解決を目指す「調停」という選択肢もあります。とはいえ、弁護士への相談は費用がかかることも忘れずに。

訴訟を視野に入れて弁護士への相談を検討しているなら、被害のレベルが客観的にわかる証拠を集めることが大切です。騒音の録音データはもちろんのこと、時間や自分が感じたことなどを詳細に書いたメモ、日記なども十分な証拠になるケースがあります。そのほかにも以下のような情報を集めることができると、客観的な証拠として役立つ可能性があるでしょう。
・騒音計や計測アプリなどで数値化した音の大きさ
・音が聞こえる時間帯
・音が聞こえてくる方向
・騒音の頻度
とくに音の大きさを数値で示した騒音レベル(db)は、当人以外にも客観的にわかりやすい基準となります。騒音レベルは無料のスマホアプリなどでも計測できるので、一度試してみると良いでしょう。
マンションにおける騒音は「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」という法律によって解決できる場合もあります。
区分所有法について簡単に説明すると、分譲マンションなど1つの建物を複数人が分割して所有する際の、個人の所有範囲やマンションの管理方法について定めた法律です。区分所有法に違反した場合、管理組合は違反者に対して法的措置をとることができます。
区分所有法ではほかの住人が不利益になるような行為に対し、当人にやめてもらうよう請求できることを定めています。それでも問題が解決しない場合は組合委員全体(正確には区分所有者及び議決権)の4分の3以上の賛成で、住戸の使用禁止や退去の請求(裁判を前提とする。)も可能です。
ちなみに、マンションの構造上の欠陥による騒音被害については、施工業者に対して損害賠償を求めることもできます。また、物件の売り手は買い手に対し「契約不適合責任」という、買い手の知らなかった欠陥に対する責任を持つことが定められており、購入してから10年(不適合を知ってから5年)までといった条件はあるものの買い手は修理の請求、損害賠償や契約の解除などを要求することが可能なのです。
「民法」によれば、騒音問題で相手に損害賠償を求めることができるとあります。
そもそも民法とは、個人間の権利や義務についての基本的なルールを定めた法律。民法の第709条では、「他人の権利や法律で守られている利益を損害したものは、それによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。これに従うと、例えば騒音によって健康的な生活を脅かされるほどの被害が生じている場合は、相手はその責任を負うというわけです。
一方で精神に多大な影響をきたして診断書があるといったケースならまだしも、そこまでではない場合、どんな被害が具体的に出ているのかを証明することは難しいため、損害賠償を求めるハードルは高いといえます。前述した客観的な騒音の証拠を集めることはもちろん、損害賠償を請求できるかどうかを事前に弁護士に相談してみましょう。
また、判断を行ううえでは「受認限度」が重視されます。これは、「集合住宅で生活する以上この程度は受け入れるべき」という限度です。受任限度を超えている場合は損害賠償などの措置を取れる可能性がありますが、限度を超えていない場合は双方の話し合いで解決する必要がありそうです。
「自分たちだけでは解決できそうにないけれど、お金や時間をかけて裁判にするほどでもない」と考える方もいるでしょう。そこで活用できる解決手段が「ADR」です。
ADRとは「裁判外紛争解決手続」の略。ADRには国民生活センターなどの行政機関が実施するもの(行政型ADR)や、民間の事業者が行うもの(民間型ADR)などがあります。ADR事業者により選任された担当者が仲介に入り、当事者同士の話し合いによる解決を目指します。
国民生活センター紛争解決委員会へ依頼する例でいえば、まずはADR問い合わせ窓口(03-5475-1979)へ連絡。担当委員が選任され、ほとんどの場合は、当事者双方と複数回の話し合いを行いながら和解による解決を促していきます。
ADRの利用は裁判よりも手続きが少なく、時間や費用といったコストを抑えられる点が大きなメリット。住人同士のトラブルなど、比較的小規模な問題はADRの方が適しているといえるでしょう。
ここまで騒音トラブルの対処法について解説してきました。しかし、どれだけ慎重にしても大きなトラブルとなってしまう場合があります。ここからは、マンションでの騒音が原因で裁判に至った例を紹介します。

2007年、下の階の住人が上に住む家族に対して、子供の走り回る音や飛び跳ねる足音に耐えられないと訴えて裁判になりました。この裁判では騒音主である上の階の家族に、30万円の損害賠償の支払を命じる判決が出されています。
「耐えがたい騒音が深夜にまで及ぶ」「苦情を伝えた被害者に対して騒音主が突っぱねるような態度を取った」など、度を超えた騒音や騒音主の不誠実な対応が被害者の受忍限度を超えたことが判決の理由となったようです。
2002年に起きたこの裁判も、上記と同じように真上に引っ越してきた家族の生活騒音が問題となりました。とくに子供の叫び声や暴れ回る音が騒がしく、被害にあった方は引っ越しを余儀なくされたとして30万円の慰謝料を請求しました。しかし、これは認められませんでした。
先ほどの判決との違いは、騒音被害が昼間の短時間だけに限られていたという点や、音の大きさが許容範囲だったという点があげられます。
2つの裁判からもわかるように、騒音を巡る裁判では音の大きさに加えて騒音の発生する時間や騒音主の対応など、総合的な観点から判断されることが多いようです。
実際には、管理会社や警察が対応してくれなかったり、訴訟での損害賠償が認められなかったりするケースも多いでしょう。
第三者に協力を依頼しても解決できない場合に考えておきたい対応を紹介します。
相手が騒音トラブルに対応してくれない場合、自宅の防音性を高めて外部からの音をなるべく遮断するという方法もあります。
壁に吸音材を埋め込むなど本格的な工事を行うと多額の費用がかかってしまいますが、貼り付けるタイプの防音シートなら比較的手軽に導入できます。
防音窓も有効な手段の1つですが、分譲マンションであっても窓は自由に変えられない可能性があるため、工事は管理会社へ確認してから行いましょう。
手軽な対処法とはいえませんが、どうしても解決をみないトラブルであれば、物理的に騒音から離れる選択肢もあります。
費用がかかることはもちろん、通勤・通学といった生活環境の変化も余儀なくされるでしょう。転居先でも騒音トラブルに巻き込まれてしまう可能性もゼロではない点にも注意が必要です。
マンションで暮らしていると、知らず知らずのうちに自分が騒音の加害者となってしまうこともあるでしょう。その際に大切なのは、苦情を言われたとしても感情的になったり慌てたりせずに、不要なトラブルを避けるためにも素直に謝罪すること。そのうえで落ち着いて相手の話を聞き、騒音の改善に努めましょう。
事前に騒音トラブルを防ぐことができれば、それにこしたことはありません。では、どうすればいいのか。
そこで鍵を握るのが、隣人と日頃から良好な人間関係を築いているかどうかです。顔見知りや普段から付き合いがあるような間柄では、そもそも騒音自体が気にならなくなることもあります。マンション内のイベントに参加してほかの住人と仲良くなっておき、顔を合わせた際には「迷惑をかけていませんか?」と声をかけたりするなどの日頃の行いが、大きなトラブルを避けることに繋がるはずです。
マンションの間取りをチェックすることも、トラブル防止方法の1つ。例えば、隣の住戸のリビングと近い部屋は寝室にしないことで、「隣のテレビの音がうるさくて眠れない」といった状態を避けることもできます。快適なマンション暮らしを手に入れるために、住む住戸を検討している段階から騒音について考慮してみると良いでしょう。


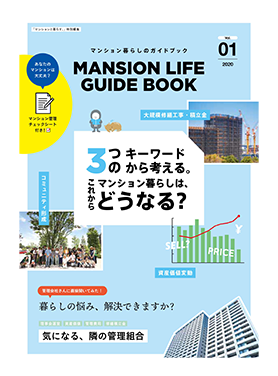
無料
ダウンロード
マンション居住者のお悩み解決バイブル!
最新マンショントレンドや理事会の知識など、
マンションで暮らす人の悩みや疑問を解決するガイドブック。
ここでしか手に入らない情報が盛りだくさん!
※画像はイメージです。実際のガイドブックとは異なる可能性があります。
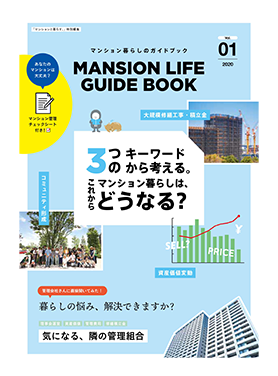 無料配布中!
無料配布中!