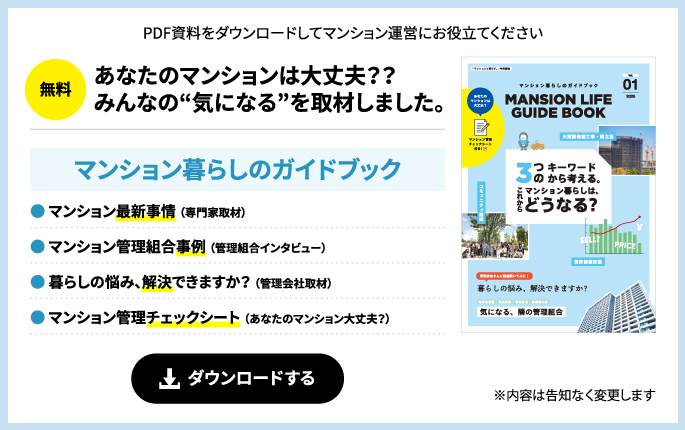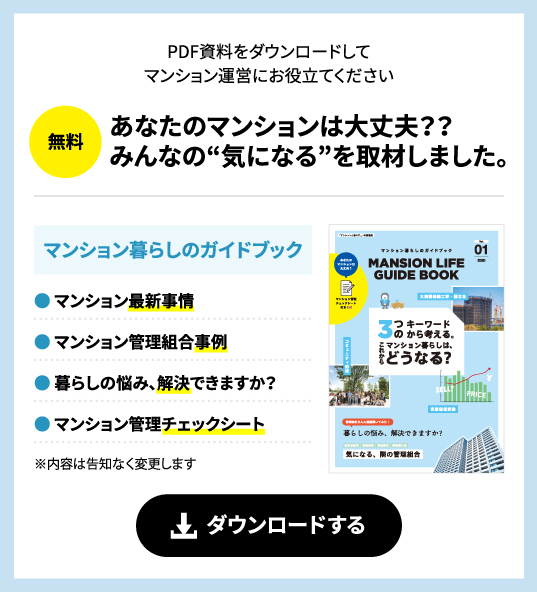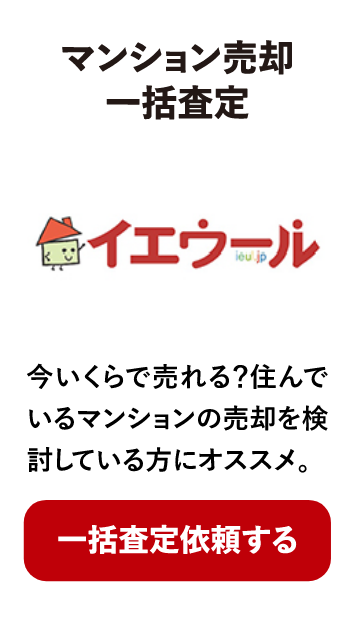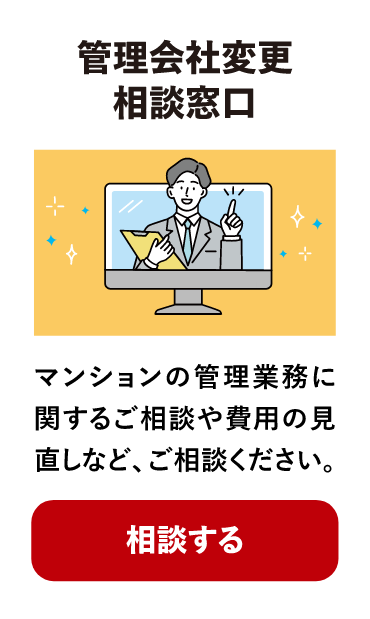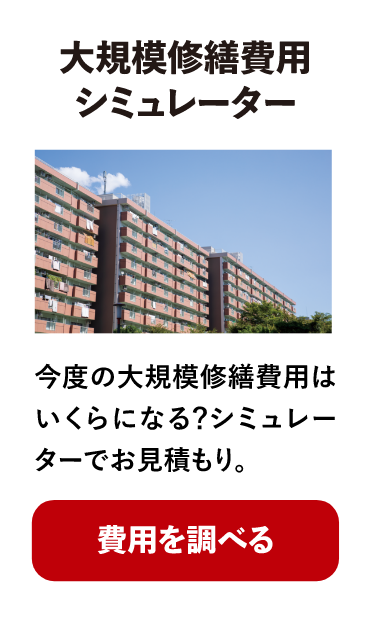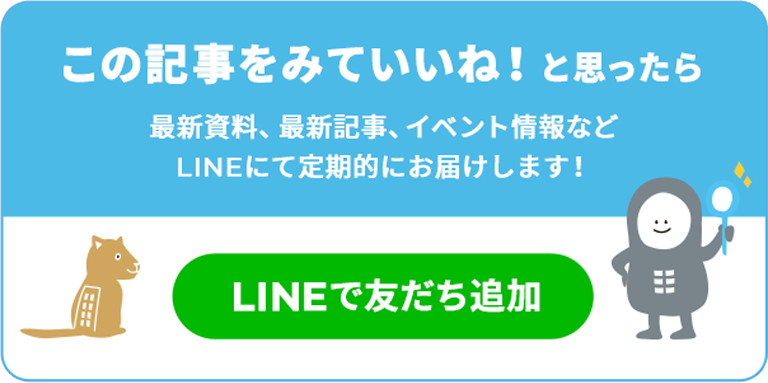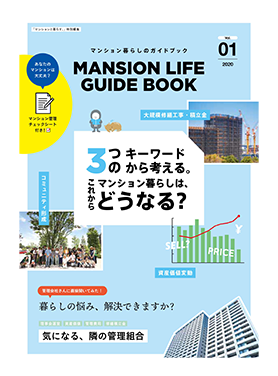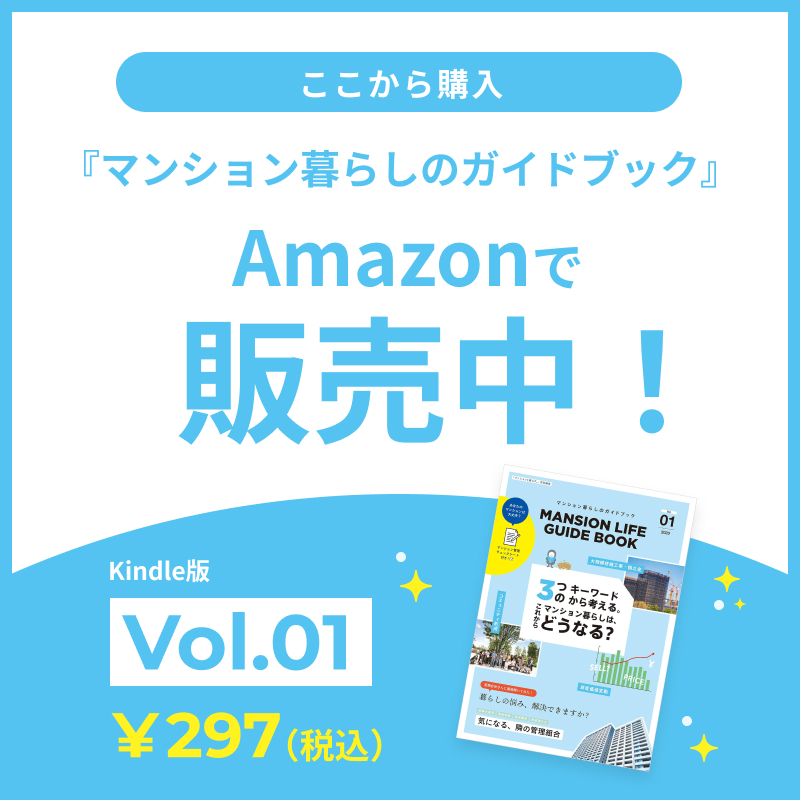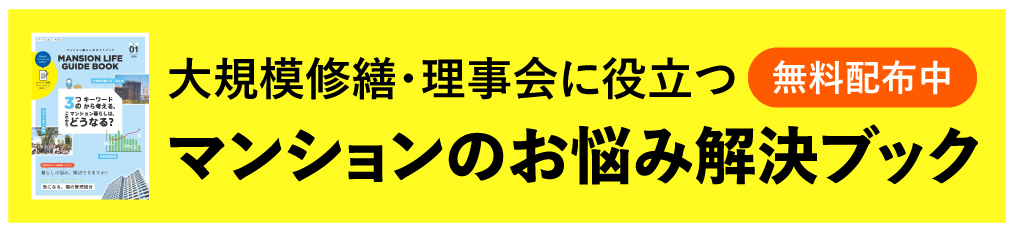自治会費や協賛金の勘定科目はどう選ぶ? 税務処理上の注意点も解説

自治会に納める会費や、イベント開催に賛同する場面で支払う協賛金ですが、会計の際にどの勘定科目として仕訳すれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな自治会費と協賛金について、仕訳方法や税務処理上の注意点について紹介していきます。
自治会費は「諸会費」や「雑費」などに仕訳する
税務処理を行う際、どの勘定科目に分類するのか明確な決まりはないものの、自治会費は「諸会費」もしくは「雑費」として仕訳するのが一般的です。特に金額が小さい場合は、雑費として処理して問題ないでしょう。
なお、個人事業主であれば事業に関連して加入している場合に限り、前述した「諸会費」や「雑費」として仕訳します。一方で自治会の加入と事業に関連性がない場合は、「事業主貸」という勘定科目で処理することになるでしょう。
ちなみに事業主貸とは個人事業主のみが使用する勘定科目で、生活費やプライベートで使う支出などが該当します。この事業主貸については、基本的に必要経費として計上できません。
自治会費は原則消費税がかからない
自治会費については、原則消費税がかかりません。そのため、自治会側は消費税を増税したからといって金額を引き上げることは難しいといえるでしょう。
ちなみに国税庁のHPには「同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します」との記載があります。つまり、お金を支払ったことによって、明確な対価を受け取る場合は消費税がかかるということ。例えば自治会主催で開催したセミナーの参加費などは、講演内容といった確かな見返りがあるため、消費税がかかるようです。
なお、消費税についての疑問は、国税局の電話相談窓口などの利用も検討してみましょう。
「協賛金」は目的によって3つに分類される

自治会からイベントやお祭りなどの運営に賛同してもらう費用として、「協賛金」の支払いを依頼されるケースもあります。
この協賛金は広告宣伝を目的とした出費であれば「広告宣伝費」に分類。協賛金を募っている事業者との関係円滑化のためであれば「交際費」に仕訳します。そして前述した2つの目的に当てはまらないのであれば「寄付金」として分類することになるでしょう。このように、協賛金は支払う目的を踏まえたうえで仕訳する必要があるのです。
なお、広告宣伝費と交際費に関しては全額を「損金」として所得から差し引くことができる、つまり節税効果があります。寄付金に関しても個人事業主に限りますが、「その年中に支出した寄付金額の合計から2000円を引いた額」を経費として計上することが可能です。
なお広告宣伝費に該当するかどうかは、「支出に見合った広告宣伝効果があるか」がポイントとなります。とはいえ広告宣伝効果は将来にならないとわからないものの、例えば同じ広告掲載枠にもかかわらずほかの協賛者は10万で自分だけ50万円を支払っていると、差額の40万円は「寄付金」に該当する可能性があるようです。
自治会費は特に金額が小さい場合は「雑費」として処理
以上、ここまで自治会費や協賛金の仕訳方法を中心にお伝えしてきました。まとめると、自治会費は「諸会費」もしくは「雑費」として処理するのは一般的。特に金額が小さい場合は、雑費として処理して問題ないでしょう。
なお自治会費は支払ったことによって明確な対価を受け取れるわけではないため、消費税はかかりません。自治会からイベントやお祭りなどの運営費用として「協賛金」の支払いを依頼された場合は、目的に応じて「寄付金」「広告宣伝費」「交際費」の主に3つに分類されることも覚えておきましょう。