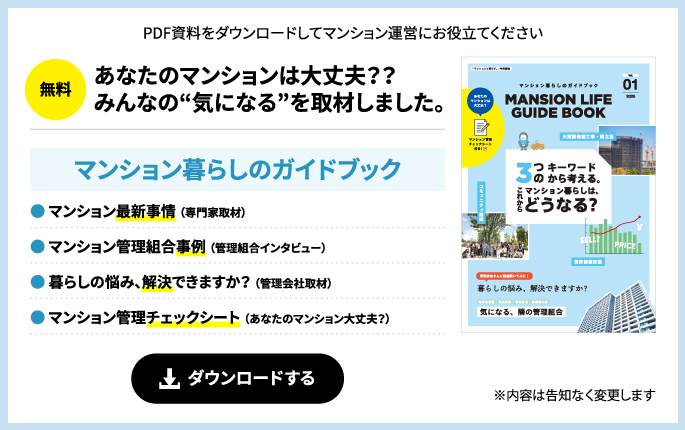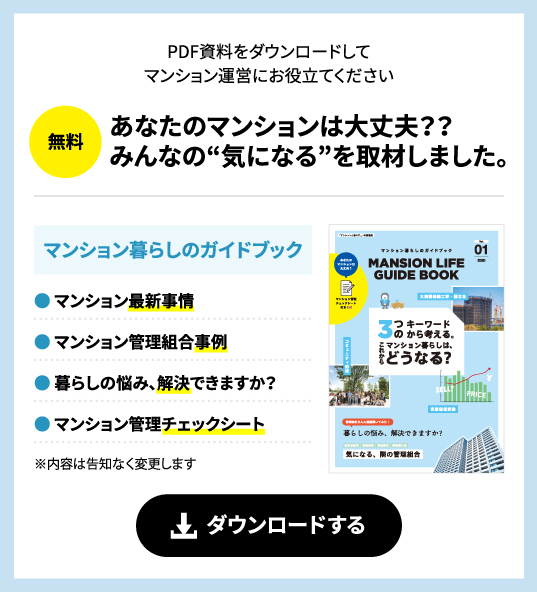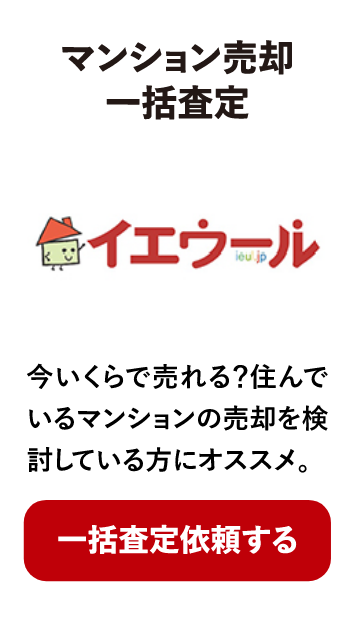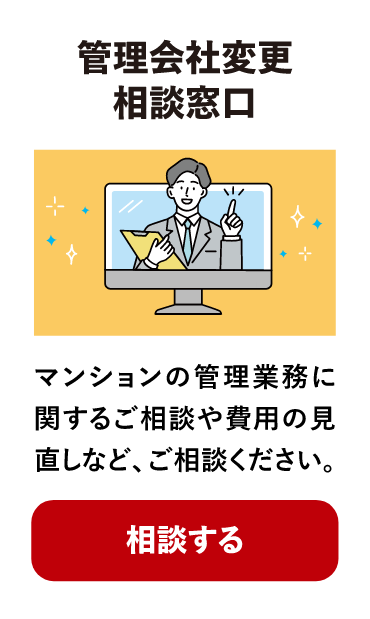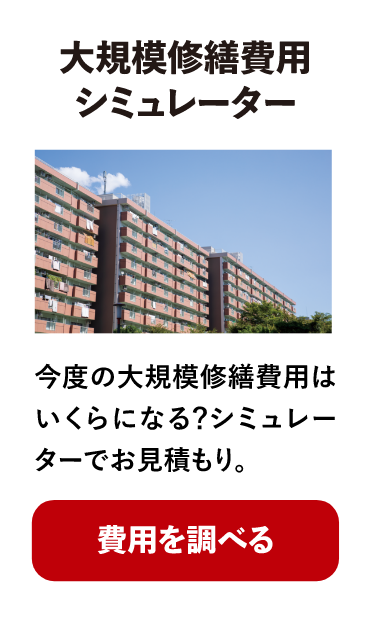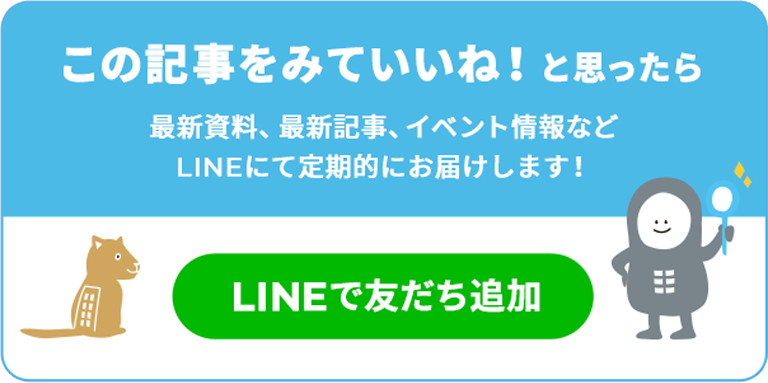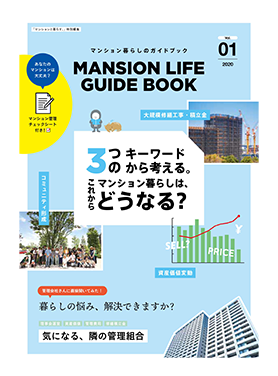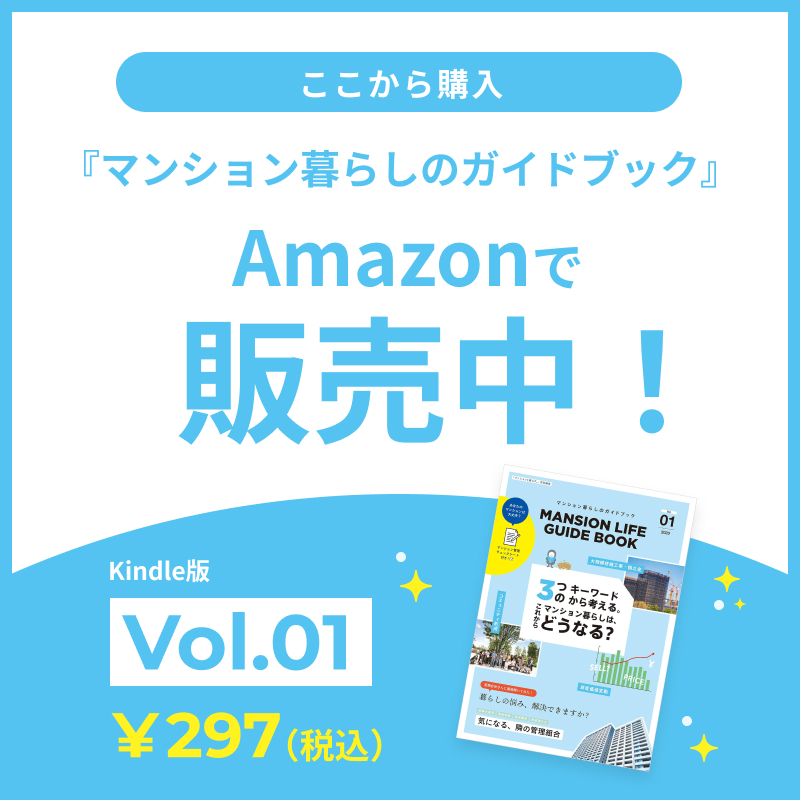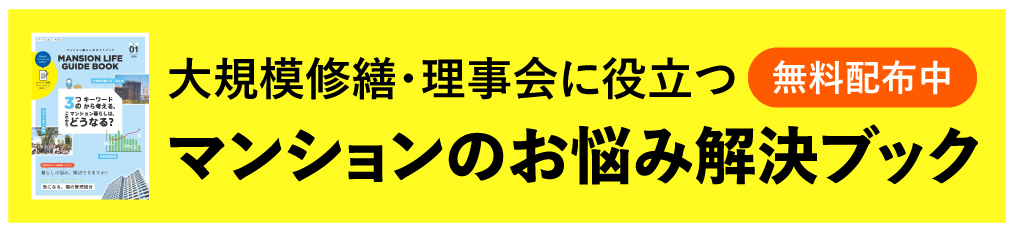連載
連載
雨漏りの修理代、火災保険でカバーできる?

雨漏りの修理費用は、火災保険によってカバーできることがあるのはご存知でしょうか。ただし、条件があります。そこでこの記事では保険が適用される条件はもちろん、雨漏りの修理を依頼するうえで信頼できる業者を選ぶポイントなども紹介していきます。
雨漏り修理を補償する火災保険は2種類! その対象範囲は?
火災保険は、その名称から「火災」による建物や家財の損害のみを補償するイメージがあります。しかし実際には、火災以外の被害により生じた雨漏りなども補償の範囲内となります。雨漏りの原因はさまざまですが、原因に合わせて適用される火災保険は主に2種類に分かれます。
まず1つ目が「住宅火災保険」です。住宅火災保険で補償する被害は、火災・落雷・ひょう・雪などによるもの。水害は対象外であるため、洪水や大雨による雨漏りは補償されません。一方で台風や強風、大雪やひょうといった「風災」を原因とする雨漏りであれば、修理費用が補償される可能性があります。
もうひとつ「住宅総合保険」は、住宅火災保険よりも補償範囲が広い保険です。物体の落下や衝突、そのほか水害などによって生じた損害なども補償の対象となります。
雨漏りに火災保険が適用される条件
続いて、雨漏りの修理に保険が適用されるための条件をみていきましょう。
主に以下の3つが上げられます。
【条件1】主に自然災害が原因であること
【条件2】雨漏りが発生してから3年以内の申請
【条件3】修理費用が20万円以上
では、それぞれの条件について詳細を解説していきます。
【条件1】主に自然災害(風災)が原因であること

火災保険の対象となるには、雨漏りの原因が「風災」によるものであると認定される必要があります。
風災とは、台風や竜巻といった強い風による被害を指し、雨や雪、ひょうも含まれます。
例え大雪によって屋根が破壊されたことが原因で雨漏りが発生してしまったケースや、台風で飛ばされた物が外壁にぶつかって雨漏りが生じたケースなどがあてはまります。
【条件2】雨漏りが発生してから3年以内の申請
火災保険に限らず、保険金の請求期限は基本的に「保険の適用が必要な事故発生から3年以内」とされています。これは、保険法により保険事故発生から3年が過ぎてしまうと、保険金請求権が消滅することが定められているため。そのほか、保険会社によっては独自の請求期限を設けている場合もあります。雨漏りの発生を確認してから、可能な限り早めに保険会社へ申請をするようにしましょう。
【条件3】修理費用が20万円以上
多くの保険会社は修理費用が20万円を超えることを保険の適用条件として定めています。雨漏りの費用は少額で済むケースもあるため、修理費用がどの程度かかるかは前もって業者に見積もりを取るなどして確認しておきましょう。
保険でまかなえる修理費用
火災保険のタイプは、上記で解説したように20万円以上の損害が出た場合に実費が支払われるタイプと、あらかじめ設定した自己負担額を超えた場合に、超過分を受けとれる免責タイプがあります。
20万円以上タイプの場合、損害額が19万円では保険金を受けとれませんが、20万円を超えていれば上限まで保険金を受けとれます。
免責タイプの場合、自己負担額を5万円にしていたとすると、損害額が4万円では保険金を受けとれず、損害額が20万円の場合は自己負担額を引いた15万円を保険金として受けとれます。
火災保険が適用されないケースとは?
一方で、火災保険が適用されないのはどんなケースなのでしょうか。
【1】経年劣化による雨漏り
まず経年劣化や老朽化など、建物が古くなったことが原因で発生した雨漏りに関しては火災保険の適用外となります。
【2】施工不良による雨漏り
マンションを建てた業者の施工不良によって雨漏りが発生してしまったケースも火災保険は適用されません。ただし、この場合は「住宅瑕疵担保責任保険」の適用で補える可能性があります。
新築マンションを建てる事業者には住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられており、購入から10年以内であれば建築会社など住宅の売主が雨漏りの修理費用について補償します。
【3】被保険者の過失による雨漏り
「故意もしくは重大な過失または法令違反で損害が発生した場合」は保険金がおりないとされています。
例えば、「ボールを窓ガラスにぶつけて割ったために雨漏りした」「修理すべきと指摘されていたのに対処しなかった」などのケースでは、保険が適用されません。
保険がおりない場合の対処法
保険金を受けとれるかどうかは自己判断ではなく、鑑定によって決まります。保険がおりないと鑑定された場合、鑑定人を替えるなどして再度調査してもらうことで、結果が変わる可能性もあります。
結果に納得できない場合や説明が理解できない場合には、鑑定人の変更も検討してみてください。
火災保険の申請手順もざっくり説明します!
火災保険の申請はおおよそ次の手順で行います。
1.保険会社、もしくは保険代理店へ連絡をする
2.保険会社からの案内・書類を受け取る
3.業者とともに現場を調査し、保険会社への書類を記入、提出する
4.保険会社から保険金を受け取る
5.雨漏りの修理工事を行い、業者へ代金を支払う
なお、保険会社が提出された書類の審査によって経年劣化とみなし、保険の適用がされないといったケースもあります。ですので、書類は雨漏りの修理を行う業者と相談しながら作成した方がいいでしょう。このため業者は火災保険を適用した雨漏り修理を経験したことがある方が頼りになります。事前に確認しておきましょう。
修理業者を選ぶポイントもあわせてチェック!

前の文で紹介した通り、火災保険の適用を受けるための書類作成は、雨漏り修理を行う業者に相談しながら進めたほうがベターで、そのためにも、やはり業者選びは大切。ここでは信頼できる業者を選ぶ際の大切なポイントを2つ紹介します。
【ポイント1】雨漏りの専門知識がある業者かどうか
依頼を検討している業者に「雨漏り診断士」の資格保有者が在籍しているかどうかは、ひとつの判断基準といえます。
雨漏り診断士とは、雨漏りの原因や修理に関する知識を持っていることを証明する民間資格。複雑な雨漏りの原因究明に精通した人間であることを証明するものですので、資格保有者のいる業者は、その分信頼があると考えられます。
雨漏りは原因を深く調査しないまま修理を行ってしまうと、一時的には防ぐことができても、その後再発してしまう可能性もあります。そこで現地での原因調査は専門的な視点で行う必要があり、その知識の証明が雨漏り診断士の資格の有無といえます。
【ポイント2】アフターケアや工事の内容が充実しているかどうか
雨漏りの原因は複雑なため、1度の工事で対処しきれない場合もあります。例えば現時点での欠損箇所は補修できたものの、その後に別の箇所から水の侵入経路が発生し、再び同じ雨漏りがおきてしまうといったケースもあります。よって例えば作業料が少し高くても、アフターケアが充実していて、ある程度の修理保証期間のある業者のほうが長い目で見ると経済的だったり、細かな調査によって徹底した修繕工事を施す業者の方が安心度も高かったりする場合があります。
雨漏りで保険を申請するときの注意点
これまで解説してきたように、雨漏り修理が火災保険で適用されるかどうかは審査の結果次第で変わります。必ず保険金がもらえるとは限りません。保険金がおりる前提で修理を依頼してしまうと、思わぬ自己負担となってしまう可能性があります。
申請が通ったとしても、保険金が支払われるまでには時間がかかります。その間は、一時的に自己負担で修理などを行う必要があるかもしれません。
また、申請は保険の有効期限内に行う必要があります。3年となっている保険がほとんどですが、事前に確認しておき、すみやかに申請しましょう。
代理申請ができない点も要注意です。保険業者が代わりに申請することはできないため、「代わりに申請します」という業者は疑ったほうがよいかもしれません。
火災保険の適用は「自然災害」による損害が大前提
雨漏り修理で火災保険が適用されるためには、「自然災害」による損害が前提です。そのため雨漏りが発生した原因によって、修理費用が補償されるかどうか変わるといえます。なお、建築時の施工不良による雨漏りであれば、火災保険は適用されないものの「住宅瑕疵担保責任保険」で補える可能性もあります。